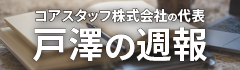戸澤の週報
2025年07月19日
「楽しむ」に至る道――知好楽と最善感
不安定な天気の1週間でした。
梅雨が明けたようで、これからは本格的な真夏日が始まります。
夏は何かが起こりそうな、何かワクワクする季節ですね。
論語に「知好楽:ちこうらく」という言葉があります。
「これを知る人は、これを好む人に如かず。これを好むものはこれを楽しむものに如かず」
知っていることは良いことだ。しかし、ただ知っているだけよりも、好きな人には敵わない。
また、ただ好きなだけでも、楽しんでいる人には敵わない。
この言葉に改めて出会って以来、考えされられることが多くなりました。
一方で森信三さんが説かれた「最善感」という言葉があります。
最善感とは「今この瞬間に起きているすべては、必要であり最善である」とする世界観です。
例えその内容が、当人にとって嬉しいことではなかったとしても、その経験は今必要なことで、世界が自分に、何かを教えようとしているということです。
この考え方は非常に深く、人に大きな影響を与えます。
・どんな出来事も自分にとって必要な試練として起きていると受け入れる受容。
・目の前に起こることは偶然ではなく必然であると、肯定的に受け止める運命観。
・環境や他人のせいにせずに、全て自分自身で受け止める主体性。
「受容」「運命観」「主体性」が定まるための基本的な世界感がこの最善感です。
このことを知ってからは、目の前に起こることの意味を考えるようになります。
世界は自分に何を教えようとしているのか?自分に何が足りないから、このようなことが起きているのか?
これらを自問することで、うっすらとそのことが起こる意義が見えてきます。
そして、知好楽を本当に実現するためには、最善感の世界観が必要なのではないかと、考えが至るようになりました。
知好楽は決して簡単なことではありません。
今の世の中ですと、自分から強く求めなければ、肝心なことを知ることがとても難しくなっています。
そのため、好きになることが難しいのです。
人はあることに対して一定の知識が入ってくると、残りを埋めたいと強く思う習性があります。
その閾値までの勉強がつらいプロセスですが、以降はすっと楽になります。
そのあたりから、苦手から得意に変わってくるので「好き」になってくるわけです。
私自身の経験ですと、ここまでは比較的イメージしやすいのですが、それではどうすれば楽しめるかです。
自分があることを好きになる頃には、だいぶ時間が経過しています。
その間には、良いことも起これば悪いことも起こります。
そのまま継続することが正しいのか、自分で疑問に思う時も出てきます。
そんな時に必要になってくるのが「最善感」だと思うのです。
どれだけつらいことが起こったとしても、それは自分にとって必ず必要なことを教えるためにあるのだと信じられること。
このことこそが、好きから楽しむに移行することができるパスポートのような気がしています。
知好楽を極めた時に、初めて本当の世界が見えてくるのではないかと、今は思っています。
そんな世界を見てみたいと思っています。