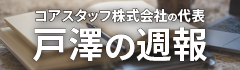戸澤の週報
2025年08月02日
判断と決断の大きな違い
関東に近づいている台風も東にそれたようで、大丈夫そうです。
西日本は変わらず灼熱の日が続いているようですが、関東は台風の影響で久しぶりに涼しさが感じられました。
毎日の仕事の中で多くの判断を行っています。
しかし、判断と決断は全く別物だと経営学者である伊丹敬之さんは言います。
決断とは判断を一応下しながらも、さらに迷った挙句に跳躍することである。
跳躍とは、実際行動に移した際に起きてくるであろう様々なゴタゴタを、自分が処理するのを覚悟することである。
実にしびれますね。心の底から共感します。
組織で何かをするかどうかの時に、やるかやらないかを判断することはさほど難しくありません。
しかし、実際に行動に移した時から、実に多くの問題や想定外の事象が起こってきます。
行動に伴う実社会の抵抗です。
多くの人は、この抵抗に負けてしまい、成果が出るまで継続できずに諦めてしまいます。
そして、その経験が次回以降の決断を鈍らせてしまいます。
しかし、本当に必要だと思うことはリスクがあるとしても、思い切って決断し、跳躍する必要があります。
その際、跳躍するための根拠になるのが、自分なりの哲学だと言います。
ここでいう哲学とは、自分の心の底からの信念と呼ぶものだと思います。
世の中に必要であるという確信。沸き立つような挑戦心。
苦労は伴うであろうが、成功するための道筋が見えていること。
このようなものが、自分の哲学と呼べそうだが、これは人それぞれであって良いと考えられる。
そして、一度跳躍したら、その後の歩みを継続させるための、哲学も必要になります。
このように考えると、決断というのは決して簡単なことではないのですが、半面で、人は状況を甘く見て決断を簡単に考えて跳躍してしまうこともあります。
しかし、そこはうまくできたもので、人間にはそのように出会ってしまった問題にしぶとく取り組み、解決する力を持っていると言います。
今の日本は経営レベルの大きな決断も、現場レベルの小さな決断の積み上げも、両方必要になっています。
特に、小さな決断の積み上げは、企業の自力になり、将来に渡って競争力を獲得するための鍵だと考えています。
頭にひらめいたことを、直ちに手を通して形あるものにして、そのアイデアを実証せずにはいられない人間のことをホモ・ファーベルと呼ぶそうです。
本田宗一郎さんは、自分のことをホモ・ファーベルであると認めています。
手を使い、頭を使い、行動に落とし込み、継続していくことでしか、我々が求めている正解にたどり着く道はないはずです。
決断とは、未来を創る行動です。そして、未来を具体的な形にするのは、跳躍のあとの「継続」であると言えそうです。
決断できる人が増えること、それが企業にも、社会にも、力強い未来をもたらす原動力になるのだと思います。